
車のバッテリーが急に上がってエンジンがかからなくなると大変困りますよね。
特にエアコンをよく使う夏の時期は車に乗ろうと思ったのにバッテリーがあがってしまった!という方も多いのではないでしょうか
この記事ではバッテリーが上がった時の対処法から、交換方法、万が一の対策について説明します
この記事を読むとこんなことがわかります
・バッテリーが上がる原因と寿命
・ブースターケーブルの使用方法
・ロードトラブルの備え
・バッテリーの選び方
・バッテリーの交換方法
バッテリーの寿命
自動車のバッテリー寿命は一般的に3年〜4年といわれますが、使用頻度や使われ方によって寿命は大きく変わりますので、一概に「寿命は○年」とはいえないのです
バッテリーにはメーカーが付けている保証期間がありますが、保証期間が2~3年だったりするので、保証が切れるタイミングを交換目安として3年で交換しましょう!といわれることがありますが、バッテリーの役割を理解していれば、使い方次第で5年〜7年くらいは交換せずに使えたりするケースもあります
※「バッテリー」=「補機バッテリー」として説明しています
ハイブリッドバッテリーの説明とは異なります
バッテリーが上がる原因は?
バッテリーが上がる原因は、オルタネーター(発電機)によってバッテリーに蓄電される量よりも使用する電気の量が増えることで、徐々にバッテリーの容量がなくなってしまうために起こります
最後はセルモーター(スターターモーター)を動かす電力がなくなってしまうことでエンジンが掛からなくなりますが、一般的に『バッテリーが上がる』とは、バッテリー内に蓄電された電気が減ってしまい、エンジンが掛からなくなった状態のことをいいます
バッテリーはエンジンを始動させるためのセルモーターや、ランプ類、エアコン、カーナビ、キーレスやカーセキュリティなど、さまざまな機能を動かすための電力として供給しています
電気を使うだけではすぐにバッテリーがなくなってしまうので、自動車にはオルタネーターと呼ばれる発電機が付いており、オルタネーターが動くことで発電した電気をバッテリーに蓄電しています
バッテリーが上がったときの対処方法
ブースターケーブルを使う
ブースターケーブルとは、バッテリーが上がってしまった車と救援車のバッテリーを繋いでエンジンを始動させることができるケーブルです
バッテリーが上がったときの対処法としてはよく知られている方法ですが、救援車がいないとブースターケーブルえない、という点はデメリットとなってしまいます
使用する方法と手順は以下の通りです
| ① | 電気供給してくれる救援車を用意 |
| ② | 故障車と救援車のバッテリー搭載場所を確認 |
| ③ | 故障者と救援車を近づける |
| ④ | 故障車のバッテリー プラス側端子に赤ケーブルを接続 |
| ⑤ | 救援車のバッテリー プラス側端子に赤いケーブルを接続 |
| ⑥ | 救援車のバッテリー マイナス側端子に黒いケーブルを接続 |
| ⑦ | 故障車のバッテリー エンジンブロック(エンジンの金属部分)またはマイナス端子に黒いケーブルを接続 |
| ⑧ | 救援車のエンジンを始動させる |
| ⑨ | 4~5分待って故障車のエンジンを始動する |
故障車のエンジンが無事に始動した後は、逆の手順でブースターケーブルを取り外します
※取り外しは手順⑦⑥⑤④の順
手順の他にもブースターケーブルを使用する際の注意点があります
クルマ同士ならなんでも繋げていい訳ではありません
・ハイブリッド車を救援車として繋がない
・ハイブリッド車同士であっても繋がない
・12Vの故障車に24V車を救援車として繋がない
・24Vの故障車に12V車用のケーブルを使用しない
・故障したハイブリッド車にガソリン車を救援車として繋げる
・ガソリン車であれば12V車同士のケーブル接続が可能
ジャンプスターターを使う
ジャンプスターターとは救援車がいなくてもバッテリー上がりの対処ができる外付けバッテリーですが、そもそも所有していている方も少ないかと思います
弱っているバッテリーや上がったバッテリーに非常用のスターターとして使えますが、最新の製品はUSB端子も付いており、モバイルバッテリーとしてスマートフォンも充電できる機能を持っている便利なモデルもあります
非常用工具と一緒にトランクやラゲッジスペースに積んでおくとより安心ですね
万が一の備えとして・・・

外出先で万が一の自動車トラブルに対応できるようなロードサービスには加入しておきましょう
家族や友人との旅行や、キャンプ、スノーボードなど、車を使って遠出する機会が多い方は特に加入しておくと安心です
バッテリー上がり以外でもよくある自動車トラブルの事例として
・キーの閉じこみ
・パンク
・脱輪
・けん引が必要な故障
・燃料切れ
など、多くのトラブルに対応可能なので、万が一の備えとしても安心です
これからロードサービスの加入を検討されている方で、「どのサービスがいいかわからない!」という方、とりあえず日本自動車連盟(JAF)のロードサービスに加入しておきましょう
日本自動車連盟(JAF)会員であれば保険適応外のトラブルにも対応可能で、多くの自動車トラブルはほとんど無料で対応してくれます
※時間帯や条件によって料金が発生するサービスもあります
しかし、加入している任意保険の特約や付随しているロードサービスの内容で十分な場合は追加でJAFに加入する必要はないかもしれません
特にロードサービスに加入されていない方にとっては、JAFは全国にネットワークを持っているので年中無休の24時間体制でサポートしてくれるのは心強いです
※アプリでロードサービスを呼べるのも簡単でうれしいですね
バッテリーの選び方
バッテリーには大きさや容量を示す型式があり、車種によって取り付けられているバッテリーは様々です
バッテリーの選び方は基本的に、元々取り付けられていたバッテリー型式と同じバッテリー型式を選択して購入すれば問題ありません
注意すべき点は長さや幅などの寸法と、バッテリー端子の配置さえ同じであれば、バッテリー容量の大きいバッテリーを選んでも問題ありません
最近ではバッテリー専門の通販サイトもあるので、愛車のバッテリー型式がわかっていればネットですぐ購入できます
国産車は適合するバッテリーのラインナップも豊富で安価なものから高価なものまで、選べる幅が多いのですが、輸入車のバッテリーは高価なうえに取り扱いが少なく、入手するのに苦労します
欧州車やアメ車に乗っていてバッテリーを探している方にはこちらがオススメです
ディーラーで取り扱う金額よりも格安で、しかも欧州車やアメ車を専門としてバッテリーを取り扱っているので種類も豊富です
探しているバッテリーで安く入手したい方は、適合するバッテリーがあるか確認してみてください
バッテリーの交換
お店に交換を頼む
イエローハットやオートバックスなどのカー用品店でもバッテリー交換は対応してくれますが、ネット通販で買ったバッテリーを持ち込んで交換を依頼する場合は注意が必要です
なぜか、そもそも持ち込みバッテリーの交換は断られる場合があるからです
店舗やお店にもよって対応は異なるでしょうが、仮に持ち込みOKでバッテリー交換してくれた場合でも高価な工賃を請求される可能性もありますので、持ち込みバッテリーの交換が可能か、料金はいくらかは事前に電話して確認しておきましょう
イエローハットやオートバックスなどの量販店でバッテリーを購入した場合は、数百円(500円程度)の工賃で交換してくれますが、それはもともとのバッテリー販売価格が高価だからなのです
よって、持ち込みの場合はバッテリーが売れていないので工賃が高くなる場合が多いです
自分で交換する
工具の使用に慣れている方であれば、実はバッテリー交換は非常に簡単な作業です
初めて交換する方でも長く見て1時間も掛からない時間であれ交換できます
(慣れていると5分〜15分で終わるような作業です)
必要なもの
・工具
(10mmのレンチが多いですが工具セットがあればなお良しです)
・手袋
(電気を通さないゴム手袋 or なければ軍手)
交換は以下の手順に沿っておこなってください
| ① | エンジンを停止させてボンネットを開ける |
| ② | ボルトを緩めてマイナス端子を外す |
| ③ | ボルトを緩めてプラス端子を外す ※取り外したケーブルの端子が他の金属に触れないよう雑巾や軍手を被しておく |
| ④ | バッテリー本体を固定している「ステー」と呼ばれる金具を外す ※車種によってステーの形状やボルト本数は異なります |
| ⑤ | ステーを緩めて古いバッテリーを取り出す |
| ⑥ | 新しいバッテリーを置いてステーを締めて固定する |
| ⑦ | プラス端子を取り付けてボルトを締める |
| ⑧ | マイナス端子を取り付けてボルトを締める |
| ⑨ | バッテリーがしっかり固定されているか確認してエンジンを掛ける |
まとめ
いかがだったでしょうか
緊急時はバッテリーケーブルを使って一時的に対処し、ケーブルを使えない場合やジャンプスターターを持っていない時はJAFなどのロードサービスを呼んで安全に対処してもらいましょう
新しいバッテリーに交換する時は愛車に適合したバッテリーを、正しい手順で交換してくださいね
自分で交換する自信がない方は、お店に行ってプロに交換してもらうことをおすすめします
たかがバッテリーですが、自動車を動かすために非常に重要な役割を担っているものです
頻繁に交換やメンテナンスをするものではありませんが、バッテリーを最近チェックしていなかった方は少し気にしてみてください
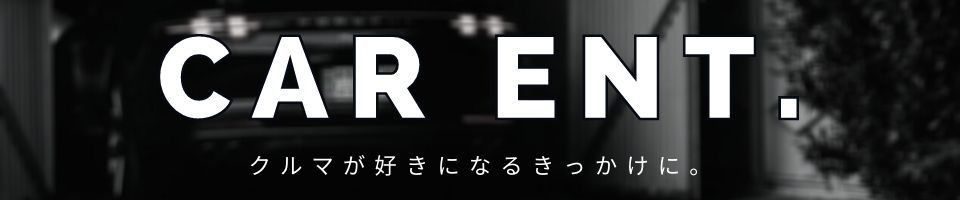

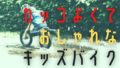

コメント